こんにちは!
アラフォー3兄弟ままのmamanieです☆
どこの本屋さんを覗いても、夏休みドリルの特設コーナーが見られる時期になりました。
皆さんのお子様、夏休み中の学習はどうされてますか?
学年や私立・公立によっても取り組み方は違うでしょうが、学校から出される宿題に+αでなにか取り組ませているのでしょうか?
昨年の長男は、新一年生とあって、学校から配布された夏休みの宿題を取り組むだけにしていたのですが、実際にはさらっと終わってしまって、親としては「これで大丈夫なのだろうか」と少し不安になったのを覚えています(笑)
今年は二年生になって、日々の学習内容や量・進行スピードも格段に変化し、息子自身も得意・不得意の実感が出てきているので、この夏休みは宿題とは別にドリルを行おうと言うことになりました。
mamanie家では、できるだけ勉強は強制しない方針なので、必要性を説明して了承を得た上で進めることになりました。
長男からの要望としては
- イラストが多いもの
- 楽しく取り組めるもの
- 難しすぎないもの
という物でしたので、あらかじめ下調べをしてから本人に選んでもらう事にしました。
くもんの夏休み ガリガリ君ドリル
子供大好き「ガリガリ君」のドリル。
特徴
この一冊で、国語・算数が復習できるドリルです。
ちょっとほそめのペラペラめくる、いわゆる「ドリル」といった冊子。
表紙は縦ですが、中身は横向き印刷です(^^)
中はオールカラー!
ガリガリ君のキャラクターやイラストが楽しく問題を出してくれます。
このドリルの面白いところが、問題のヒントがページの一番下をめくると見ることができるのですが、その案内が「アイスを食べたらヒントが出てくるよ!」とガリガリ君アイスならではの表現方法なんです!
これは大人の私でもワクワクしましたし、小技が効いていて感心しました。
問題の難しさは、至って普通の学校で取り組んでいるプリントに近い印象を受けました。
問題と問題の感覚や余白も見やすくすっきりしています。
アイスの棒を使ったパズルと計算式を組み合わせて、考察させるような問題もありました。
付録は、勉強のご褒美として、子供が喜びそうなキラキラシールです。
夏休みドリル 【田近洵一】
一見、学研から出ている「ドラゴンドリル」のシリーズかと思いましたが、こちらは「永岡書店」さんから出版されているものです。
学習指導要領対応。
特徴
一冊で国語・算数の復習が出来る、本の様な見開きのドリルです。
中はオールカラー。
9大付録付きです。
- かけ算九九表
- 二年生漢字表
- 一年生漢字表
- 自由研究アイデア集
- 頑張ったねシール
- 長さ・かさの単位読み方表
- 国語ことばパズルシート
- 算数ぬりえシート
- 何でも観察シート
ドリルの中にはドラゴンは出てきません(笑)
表紙と「頑張ったねシール」にドラゴンが採用されています。
学校で実施されるカラー版のテストをイメージされると良いかと思います。
国語は1年生の漢字の復習もサラッと用意されているのも良いポイントです。
夏休みドリル マインクラフト
このゲームにはまっている子も多いのでは?
特徴
この1冊で、国語・算数・英語 の復習が出来る様になっています。
英語に関しては、まだ学校でも家庭でも取り入れていないので、我が家では復習にはなりませんが、とっかかりとしてよいかもしれません(..;)
見開き型の本タイプのドリルで中はオールカラー!
文字は大きめの太文字なので読みやすかったです。
ドリルというよりはテキストといった感覚で、3教科が盛り込まれている割には薄手なので負担なく取り組めそうな印象。
紙質は厚手でしっかりしています。
出題問題はほとんどマイクラのキャラクターやイラストを使用しているので、マイクラの世界観そのままで足し算やグラフの問題が作成されています。
気になった事としては、カラフルだし、キャラクターが満載なのでごちゃついた印象を受けました。
また、答えを書き込むスペースが少し狭めかなとも思います。
問題数は少なめなので無理なく楽しく取り組みたいお子様向けかなと思います。
選んだのは「夏休みドリル【田近洵一】」
息子が選んだのは、ドラゴンの表紙の「夏休みドリル」。
一年生の時に学研から出版されている「ドラゴンドリル」にドはまりしていたので、私としては納得のチョイス(笑)
本人曰く、「わかりやすそう。」とのこと。
漢字表はトイレに。
観察シートはせいかつかで育てている植物やザリガニで使用する予定です。
国語と算数の復習が出来るという「夏休みドリル」。
それだけでは無く、結果的にせいかつかの勉強が自然と取り組めたり、親子を悩ませる「自由研究」のアイデア集が付録だったりと、復習ドリルだけじゃない大きな価値があるように感じました。
これは親目線ですので、実際に子供が取り組んで何を学ぶのかは個人差があると思います。
親としては、このドリルを活かした学びができるよう、無理のない範囲で付き合ったり見守ることにしたいと思います。






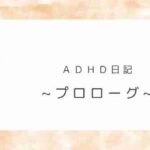
コメント